知らない場所に旅に出たくなる物語だ。
読み進めるほどに、ふたりが歩くイギリスの片田舎の風景が目に浮かび、心の雑音がすっと消えていく。
離婚し職場を離れた「私」と、親代わりだった祖父母を亡くしたちどり。
傷を抱えた30代後半の女性ふたりが、イギリス西端の静かな町へと旅に出る。
大きな事件は起きない。
ただ観光して、食べて、話をして、夜にはお酒を飲む。
そんな日が続いていく。
けれどその何も起きない時間こそが、この時のふたりにはいちばん必要なのだろう。
そんな淋しさを背負ったふたりには「祭りのあと」という言葉が頭に浮かぶ。
人生の賑やかな時間が過ぎ去って、心にはしんとした気持ちが残っている。
「後悔している」とか「あの頃に戻りたい」とは違う。
祭りの翌朝のように、キラキラとした余韻と今の気持ちの狭間で戸惑っている--そんな感じだ。
この物語が教えてくれるのは、傷ついた心は一直線に回復していくのではない、ということ。
行きつ戻りつしながら、ときにはかさぶたを引っ掻いて再び血をにじませながら、ゆっくりと傷を自分の体の一部として受け入れていくしかない。
だからこそ、それにふさわしい場所が必要なのだ。
この物語のふたりのように。
淋しいときは静かな場所、悲しいときは安心して泣ける場所。
無理して賑やかな場所に出向く必要はない。
心を常に楽しさでコーティングする必要なんてないのだ。
落ちるときは、とことん落ちてみる。
あとは、浮力に任せて水面に上がってくれば良い。
私も時々旅にでる。
といっても、半日ほどのささやかな旅だ。
なにもかもが嫌になったとき、海を見るために車を走らせる。
人がたくさんいる場所だと孤独感はより一層際立つけれど、誰もいない海は不思議と心が落ち着く。
目の前に広がる大きな空間と波の音。
浜辺にはおじいさんと年老いた犬。
ゆっくりと時間が流れてゆく。
世界にはこんな場所もあるのだ。
あってもいいのだ。
そう思うと、今の自分の淋しさも受け入れられる気がする。
場所だけの話ではない。
本も映画も音楽も、今の気持ちに寄り添ってくれるものを選べば良いと思う。
それは10年前の映画かもしれないし、100年前の音楽かもしれない。
もしあなたが今、ひとりで淋しさを抱えているのならば、この本はきっと優しく包み込んでくれるはずだ。

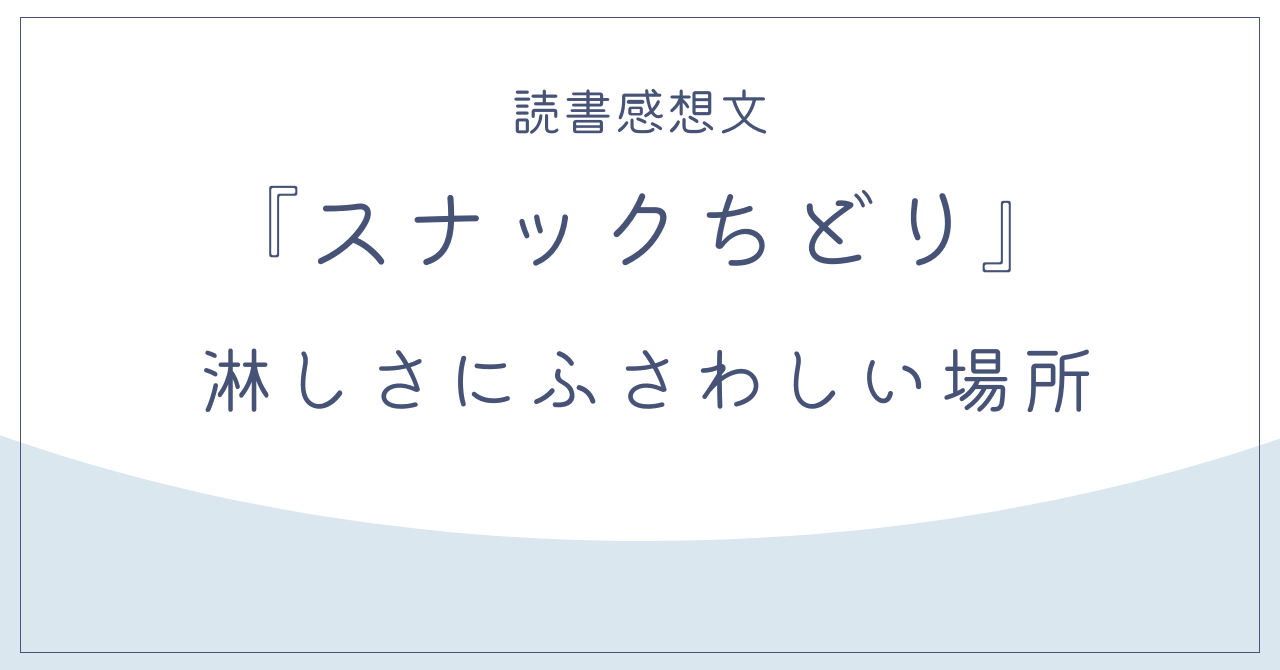

コメント