言葉とはなんだろう。
とても身近なのに、考えれば考えるほどわからなくなる。
日本語はたった五十音の組み合わせでできている。
それなのに、そこから生まれる言葉は無限に広がり、人の心を揺さぶる。
私たちはその言葉を通して喜び、傷つき、絶望し、救われる。
では、言葉の本質とは何なのか。
本書『ゲーテはすべてを言った』の主人公・統一は、ある日レストランで「ゲーテが言った」とされる言葉に出会う。
しかし、ゲーテ研究者である彼は、その言葉を知らない。
彼にとって、それは単なる違和感ではなく、探究すべき問いへと変わる。
本当にゲーテはその言葉を言ったのか?
その出典はどこにあるのか?
こうして彼の「言葉探し」が始まる。
多くの人にとって、そんなことは些細な問題だ。
「へえ、ゲーテはそんなことを言ったのか」と流せば終わる話だ。
しかし、統一は違う。記憶を探り、文献を漁り、かつての恩師や友人を訪ねてまで、その言葉の真実を求める。
それは単なる研究者としての意地なのか?
それもあるかもしれない。だが、彼は言葉を追い求めることそのものを楽しんでいるようにも見える。
それは知的な遊びであり、純粋な知の探求だ。
「名言とはまさしく有名な偉人による有名な言葉のことだが、実際には無記名性と無個性がその条件となっている」
鈴木結生:『ゲーテはすべてを言った』
この一節は、統一の探究の本質を表しているように思う。
ある人が言った言葉は、時間とともに歴史の中で磨かれ、当時の背景や語られた状況が削ぎ落とされ、やがて純粋な「言葉」として残る。
そして、それが普遍性を持ったとき、名言となり、真理として語り継がれる。
しかし、ここで疑問が生まれる。
言葉が世界を創るのか。
それとも、世界が言葉を創るのか。
統一の言葉探しは、単なる研究ではなく、「言葉の本質とは何か?」という問いそのものだったのではないか。
言葉は意思の伝達やコミュニケーションを超え、人間の思考そのものを形作る。
私たちは言葉を操っているつもりで、実は言葉に操られているのかもしれない。
人工知能が膨大な言葉を生み出し、電子空間に無数の言葉が溢れる時代。
人間が発した言葉すら、もはや誰が言ったものかわからなくなりつつある。
それでも、私たちは言葉を探し続ける。
もしかすると、それは祈りに似ているのかもしれない。
何もできない私たちは、言葉を通して祈ることしかできない。
言葉は祈り。
言葉は神。
言葉が普遍性を持ち、誰のものでもないものになったとき、それは世界を形作る力を持つ。
そして、それが真理にまで昇華されたとき、それは「すべてを言った」とも言えるのかもしれない。
だからこそ、ゲーテは「すべてを言った」のかもしれない。

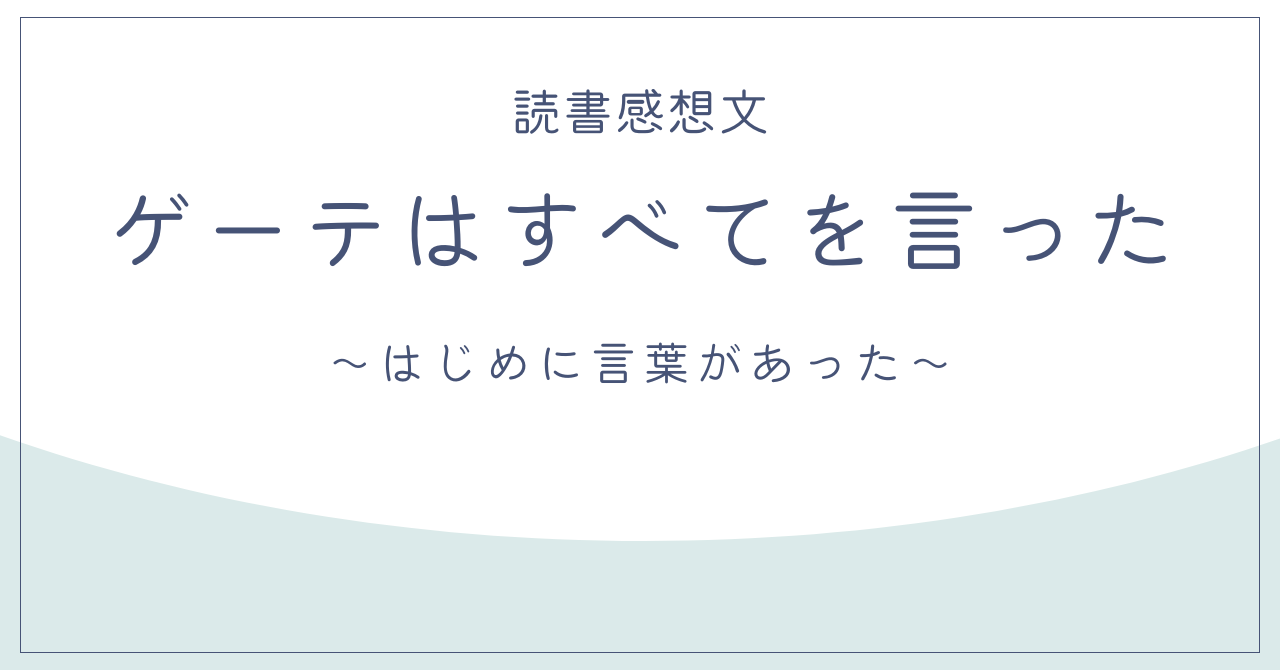


コメント